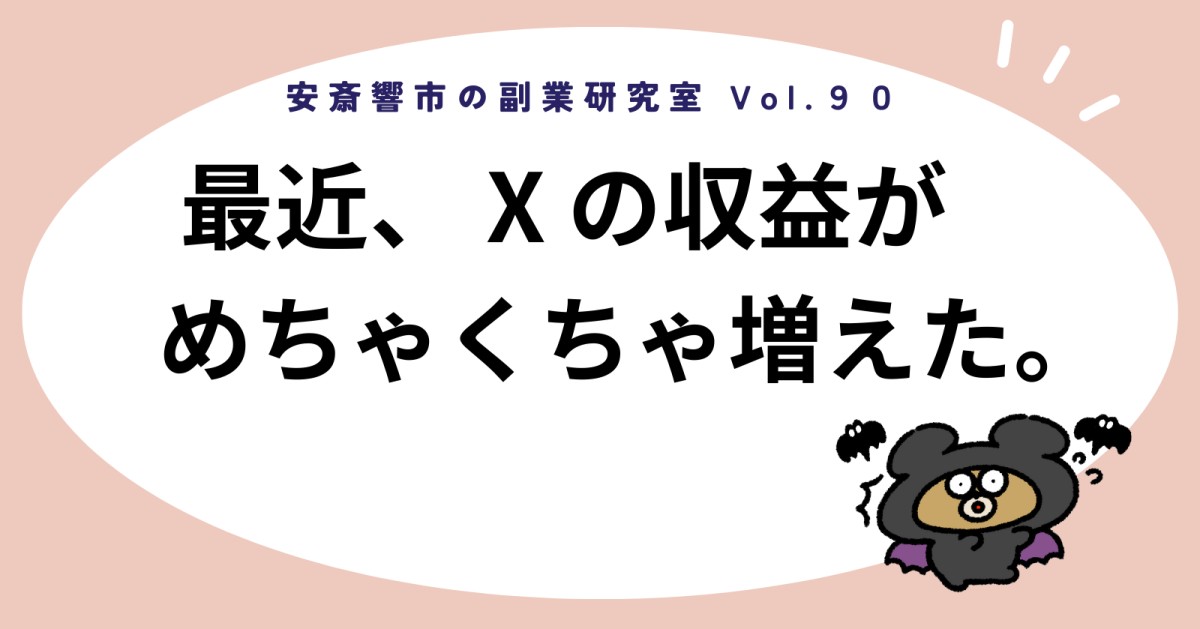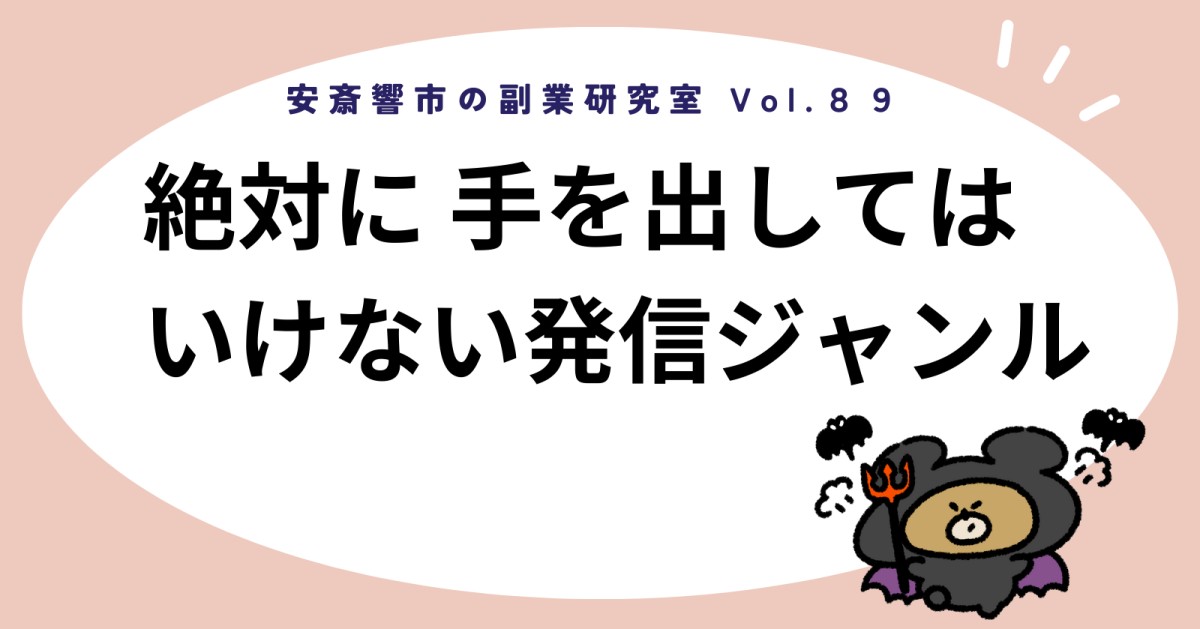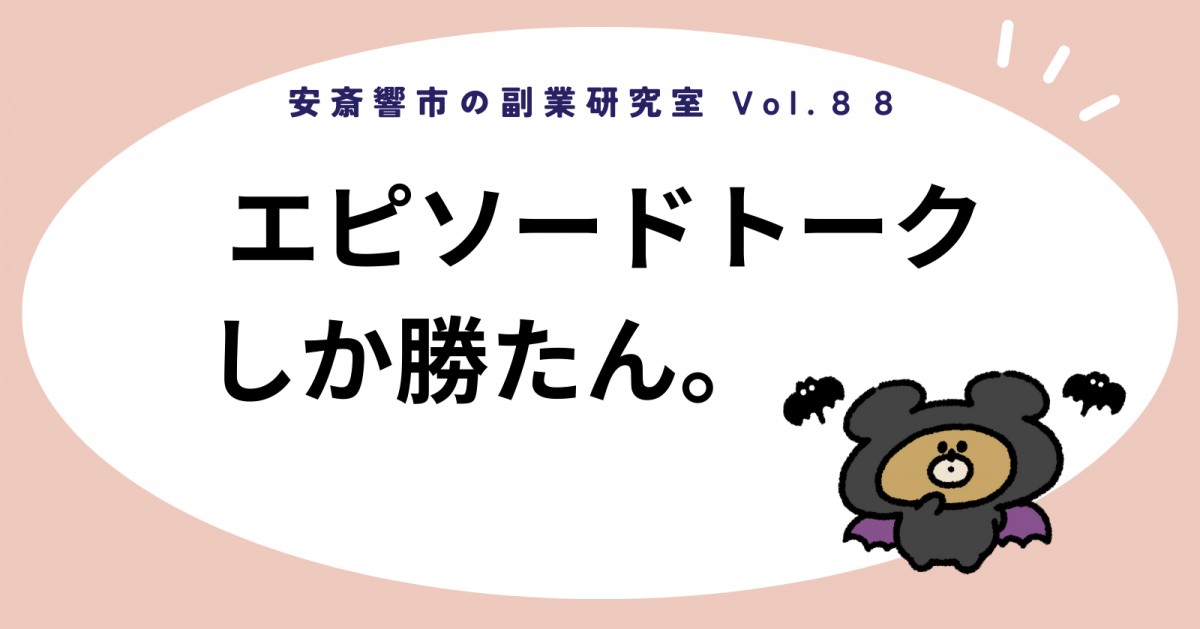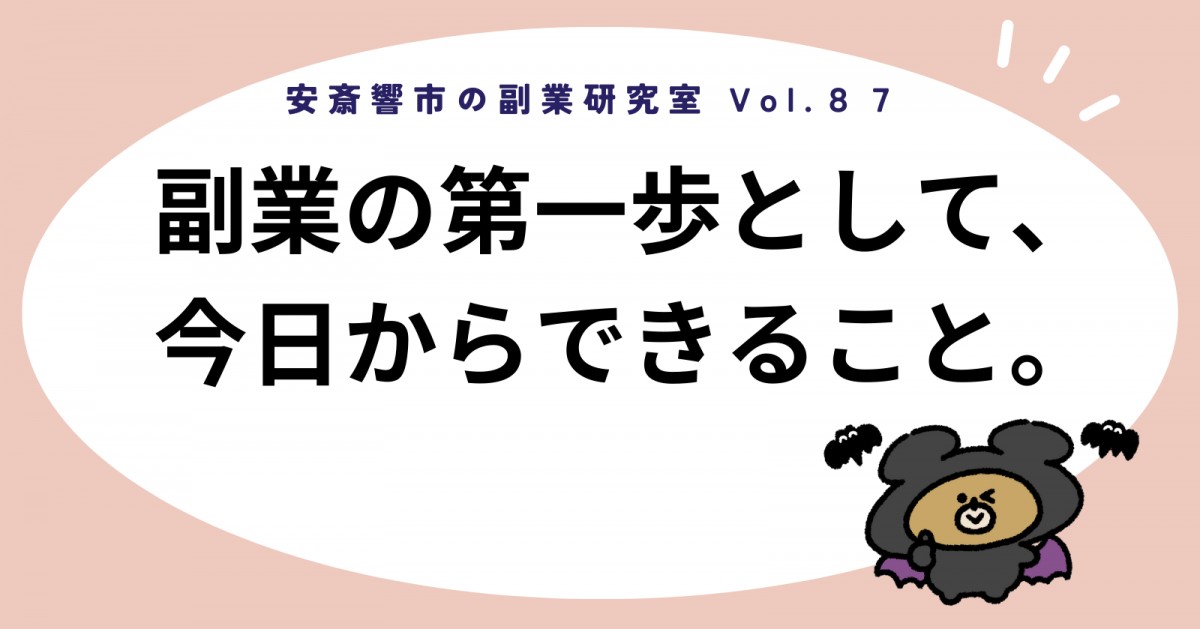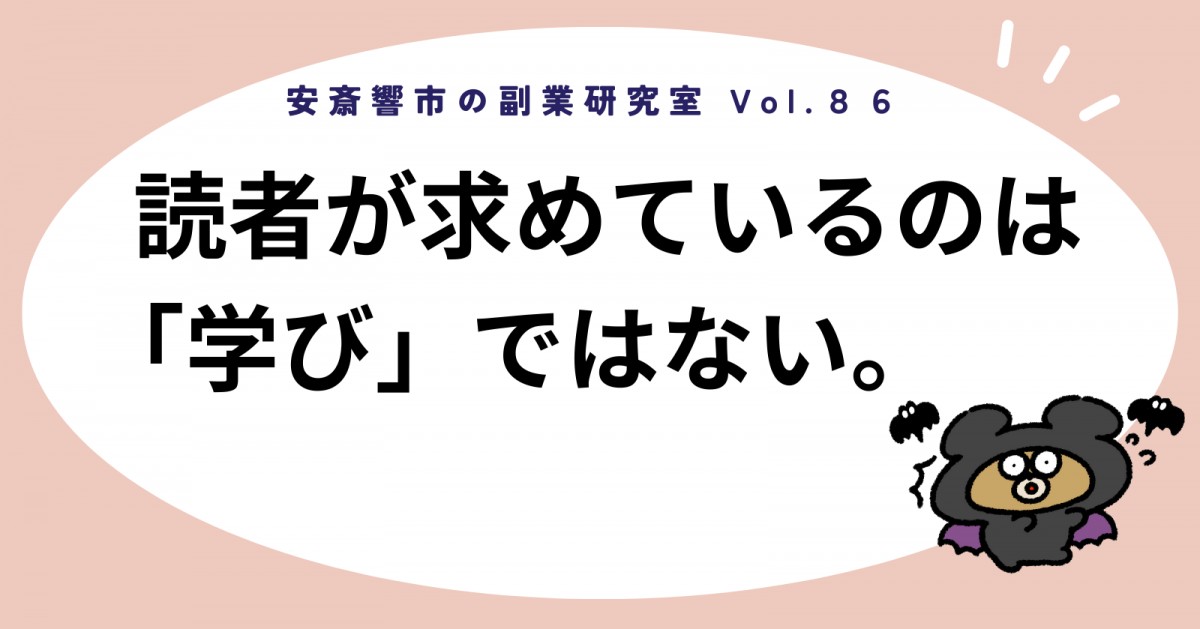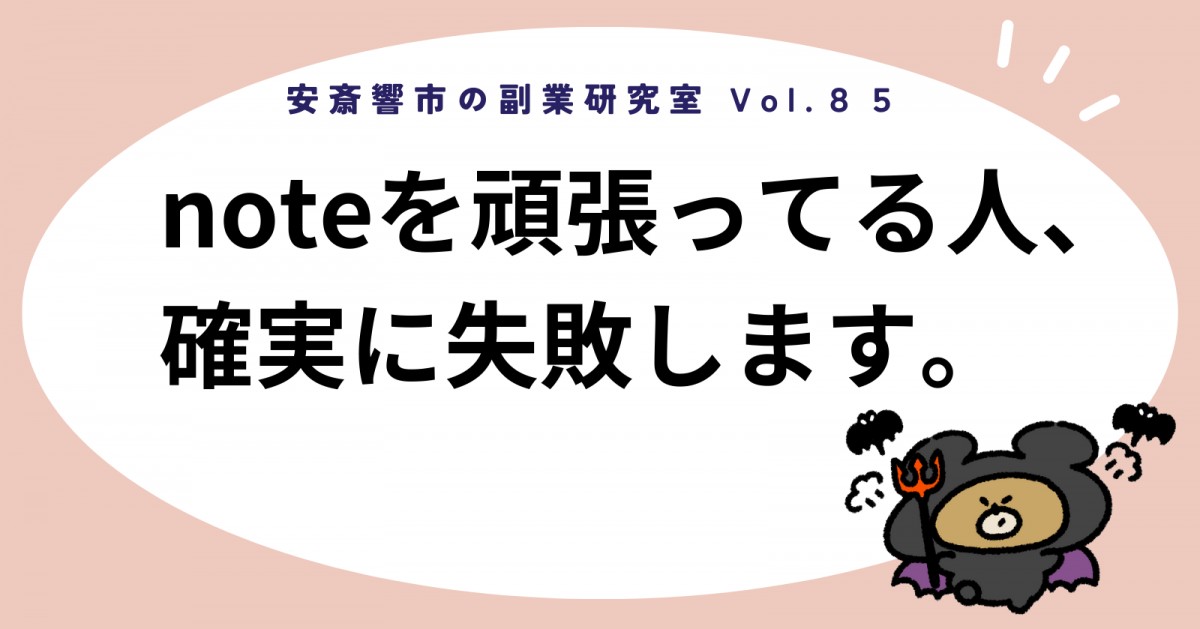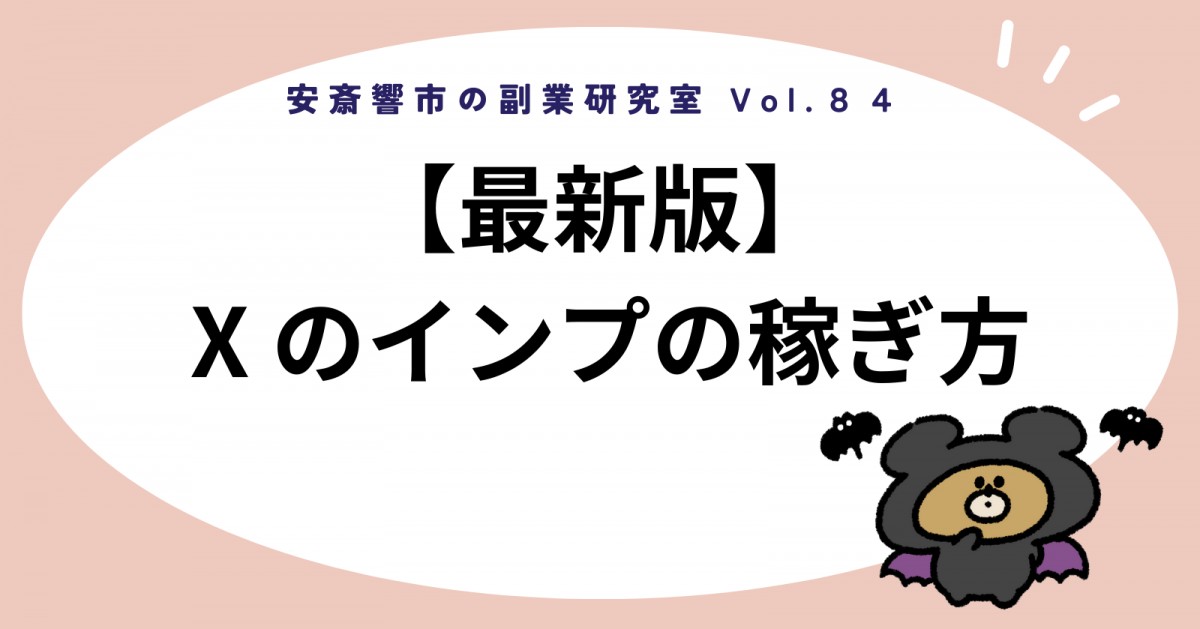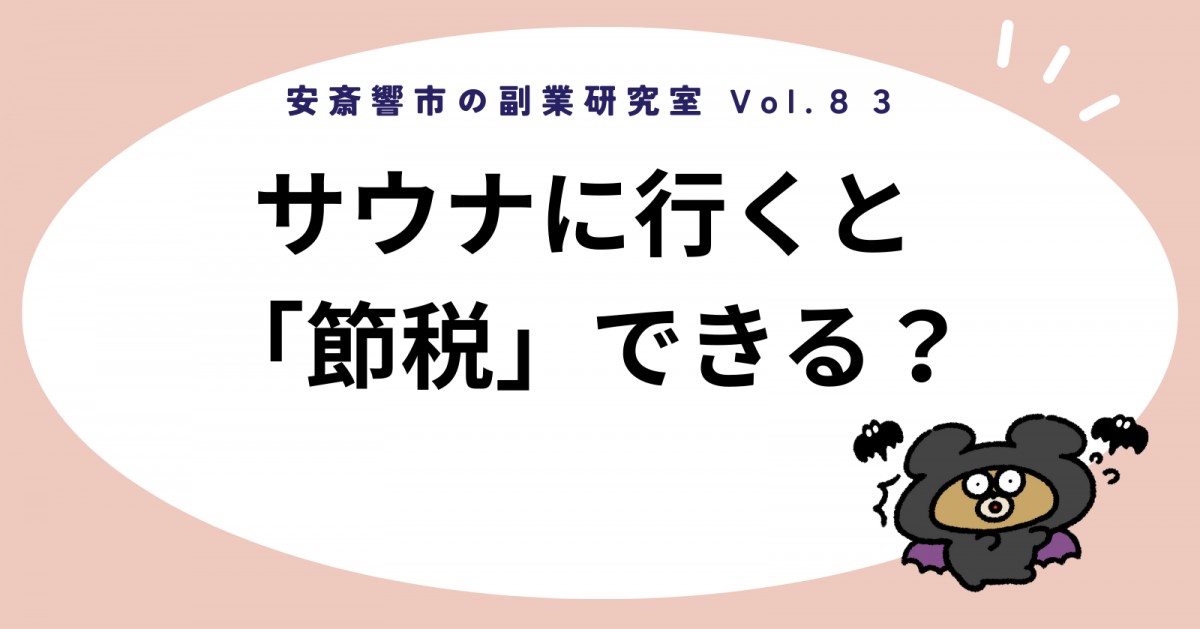Vol.37:これが本命!? AIでお金を稼ぐ「新手法」
まさか、こんな方法でお金が稼げるとは思ってませんでした。この流れがどこまで来るのかは分かりませんが、押さえておいて損はない情報です。
あーーーーー、びっくりした。
何がって、コレですよ。
2ヵ月ほど前に、note社が「クリエイターにAI学習の対価を還元する実証実験を始める」と発表しました。ちょうど、GoogleとのAI関連の資本提携を始めてすぐのことです。
「AI学習の対価を還元する」ってどゆこと??
という気もしますが、
要するに、あなたが書いた文章をAIに学習させる代わりに対価としてお金をもらえるという仕組みを作ろうとしている(作れそうかどうかの検証をしている)ということです。
note社は、noteプラットフォーム内で公開されて記事に関して、クリエイター本人が「AIの学習に使っていいですよ」「AIには使われたくないですよ」という意思表示をして、勝手に無制限に学習させないようにするスキームを作ろうとしているように見えます。
昨今の「ジブリ風画像」しかり、AIの学習って権利関係どうなってんんだぁ!? と物議を醸してますからね。
-
「私は自分の作品をAIに学習させたくないです」という意思表示=オプトアウトをして、AIの学習を阻止する。
-
「私は自分の作品をAIに学習させてもいいですよ」という意思表示をする代わりに、AIが学習した分だけ対価としてお金を受け取る
こういうことができれば理想的だよね、ということだと思います。

Googleという巨大資本のバックアップのもと、新しいことに挑戦している姿勢は素晴らしいと思います。
ただ、正直言って、この「意思表示」って単なる「意思表示」でしかなく、現状の法律だといくら「私は自分の作品をAIに学習させたくないです」と自分が言ってもAIは学習し放題なので、noteという小さな会社が正義と倫理に基づいてこの活動をしたところで全世界的に見たら焼け石に水...... という気もします。
「インターネット上に自分で公開した情報を、AIに学習させたくない」って、基本は不可能ですから。
意思表示をしようが、しまいが、自分が作った作品はAIに食べられてしまいます。それが現実です。
「パクリ」「盗作」を防ぐために著作権などの法整備は必要ですが、「AIの無断学習」は現状防ぎようがありませんし、それは過去散々Googleがやってきたことでもあるので、この「意思表示」にどれだけの意義があるのかは私には分からないです。
さて、本題。
以上の前提のうえで、「意思表示」の有無はあまり関係ないと私は考えているものの、「お金をくれる」というなら、もらっておくに越したことはありません。(現金やなw)
どっちみち、「意思表示」しようが、しまいが、無断学習されてしまう可能性はあるんですから、「AIに食わせたければ全然食わせていいですよ。その対価としてお金をくれるって言うなら、もらっときましょう」ということです。
具体的に、今回、私はnote社から「何円」のお金を配布されたのか?
ここがポイントです。たぶん、びっくりしますよ。